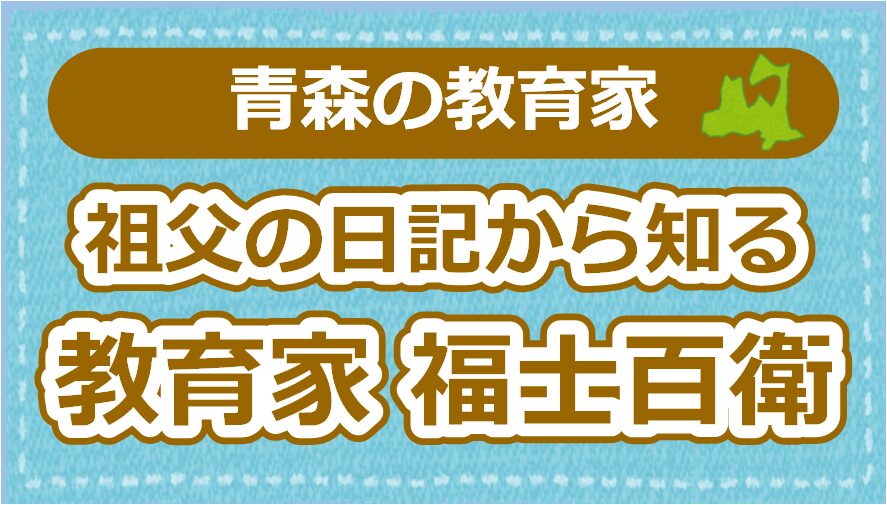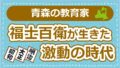亡き祖父が書き残した日記を今読んでいます。
今読んでいる箇所は戦前のあたり。祖父が中学時代を振り返った日記です。
その中に「福士百衛校長先生」という名前が登場するのですが、この人物に興味を引かれました。
フルネームで書かれていることから、祖父はこの福士校長に深い敬意を抱いていたのではないかと思ったのです。
気になって調べてみると、福士百衛氏は青森県の教育界で功績を残した教育者だったことがわかりました。
(ちなみに「百衛」は「ももえ」と読むそうです)
祖父の弘前中学時代の校長先生
祖父の日記によれば、福士百衛氏は祖父が弘前中学(現在の弘前高校)に在籍していたときの校長先生でした。
詳しいエピソードは書かれていませんが、祖父は福士校長にたいへんお世話になったようです。
少し話がそれますが、昔の文献を読んでいると、校長先生は地域社会と深く結びついた指導者のような存在だったという印象を受けます。
(現代の校長先生は、どちらかというと学校という組織の運営者という役割が強い気がします)
おそらく、福士百衛校長も威厳があり、教育に情熱を注ぐ人物だったのでしょう。
だからこそ、祖父の記憶に深く刻まれていたのかもしれません。
福士百衛氏のプロフィール
福士百衛氏についてさらに調べると、国立国会図書館デジタルコレクションで多くの文献がヒットしました。
一番古いものは明治時代後期のものも!
その中でも、『青森県読書運動明治大正史 : 郷土創造と焚火仲間』に経歴が詳しく掲載されていたので、簡単にまとめてみました。
福士百衛氏の年表
| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 出来事 |
| 明治23 | 1890 | 0 | ・南津軽郡石川町薬師堂(現在の弘前市薬師堂)に 神官の長男として生まれる |
| 明治43 | 1910 | 20 | ・青森師範を卒業し、東京高等師範学校に進学 |
| 大正3 | 1914 | 24 | ・東京高等師範学校 国漢科卒業 |
| ・秋田中学、秋田師範、青森中学教諭を歴任 | |||
| 大正14 | 1925 | 25 | ・青森県最初の県視学に任命 |
| ・その後しばらく教壇を離れて社会教育主事、地方視学官、 初代県立図書館館長を務める | |||
| 昭和5 | 1930 | 40 | ・教育現場に復帰、県立八戸高等女学校、野辺地中学の校長を歴任 |
| 昭和12 | 1937 | 47 | ・弘前中学の校長となる(9年間勤務) |
| 昭和21 | 1946 | 56 | ・退職 ・その後、薬師堂熊沢神社、石川町乳井神社の神官を務める |
| 昭和23 | 1948 | 58 | ・神官を務める傍ら、弘前高校PTA会長を務める |
| 昭和25 | 1950 | 60 | ・弘前高校PTA会長を退任 |
| 昭和30 | 1955 | 65 | ・社会教育功労者として文部大臣賞を受ける |
| 昭和33 | 1958 | 68 | ・死去 |
福士百衛氏が弘前中学の校長を務めたのは昭和12年(1937)から昭和21年(1946)まで。
祖父が在学していた期間と重なります。
神官の家に生まれた教育者
この年表をまとめていて驚いたのが、福士百衛氏の華麗なる経歴です。
- 神官の家に生まれる(晩年も神官を務める)
- 東京高等師範学校(現在の筑波大学)を卒業
- 社会教育功労者として文部大臣賞を受ける
神官の家に生まれたということは、地域の模範となるよう厳格な教育を受けたはずです。
幼い頃から学問に励み、その努力が東京高等師範学校への進学につながったのではないでしょうか。
さらに晩年には、青森県の教育界に貢献した功績が評価され、文部大臣賞を受けるほどの人物となりました。
祖父と福士百衛校長のつながり
祖父の日記を振り返ると、福士百衛氏が弘前中学の校長を務めていたのは教員としてのキャリアの最終盤です。
豊富な経験と教養を活かし、生徒たちを導いていたことが想像できます。
冒頭で、「祖父は福士校長に深い敬意を抱いていたのでは?」と書きましたが、もしかすると祖父の人生において、福士校長の言葉や教えが重要な意味を持っていたのかもしれません。
それを確認する術はありませんが、だからこそ想像するのが興味深いですね。
福士百衛氏について、また調べてみたいと思います。
本記事のまとめ
- 祖父の日記に登場した福士百衛氏は、青森県の教育界に大きな足跡を残した人物だった。
- 神官の家に生まれ、青森県師範学校で学んだ後、東京高等師範学校を卒業。
- 弘前中学の校長として、祖父をはじめ多くの生徒たちを導いた。
- 晩年には神官を務めながら、社会教育功労者として文部大臣賞を受賞。
祖父の人生にも、福士百衛氏の存在が何らかの影響を与えていた可能性があります。
これからも、福士百衛氏の足跡を追ってみたいと思います。
参考文献
<国立国会図書館デジタルコレクション>
- 間山洋八 著『青森県読書運動明治大正史 : 郷土創造と焚火仲間』,津軽書房,1981.1. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12276912 (参照 2025-03-25)
※国立国会図書館デジタルコレクションの閲覧には、利用者登録が必要な場合があります。
<ウェブサイト>