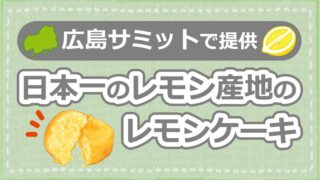 食べる飲む
食べる飲む 【広島サミットで提供】日本一のレモン産地で作った「瀬戸田レモンケーキ島ごころ」
先日、近所のスーパーで開催されていた地方物産フェアをのぞいてみたところ、「瀬戸田レモンケーキ島ごころ」という名前のお菓子が目にとまりました。スーパーの宣伝文句は「G7広島サミット2023で提供」。先進国の首脳たちが食べたかもしれない味、ちょ...
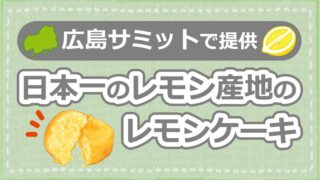 食べる飲む
食べる飲む 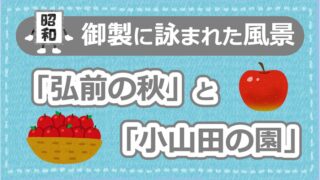 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 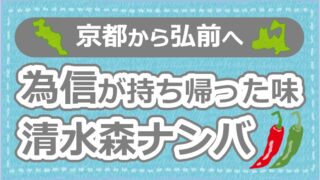 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 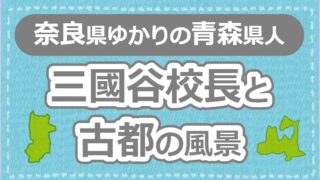 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 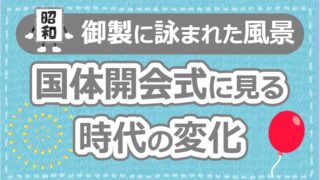 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 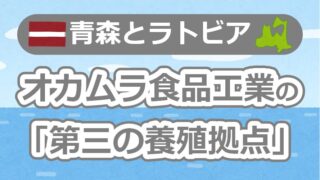 ニュース
ニュース 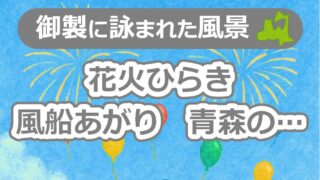 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 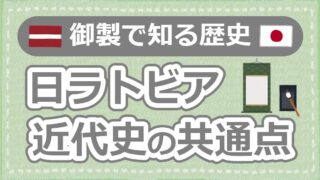 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 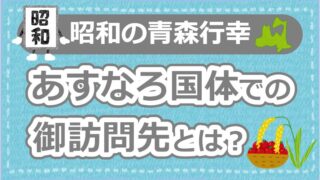 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 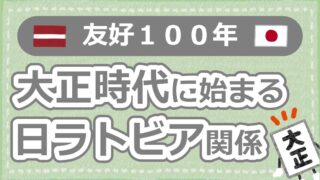 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ