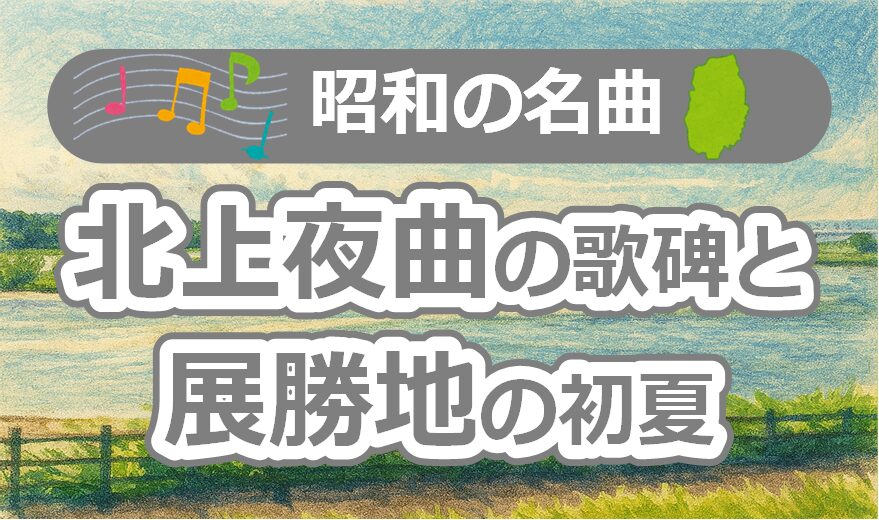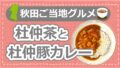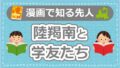2023年6月、岩手県北上市の展勝地レストハウスを訪れた際に、偶然ある歌碑を見つけました。
それは、昭和の名曲として多くの人に親しまれてきた「北上夜曲」の歌碑でした。
この記事では、「北上夜曲」の歌碑についてご紹介しながら、北上川の美しい風景や若き日の作詞・作曲者について取り上げていきます。
レストハウス脇に佇む「北上夜曲」の歌碑
展勝地レストハウスで名物の西わらび入り蕎麦を買い、外に出たときのこと。
レストハウスを出て右手の道を歩いていると、ひときわ目を引く立派な碑が視界に入りました。
そこには「北上夜曲」と刻まれ、作詞・作曲者の自筆による歌詞と楽譜が彫られていました。

碑のそばには「北上夜曲メロディー操作盤」というボタンが設置されており、押すとメロディーが流れる仕組みです。
実際に押してみると、懐かしさを感じさせる旋律がその場に響き渡りました。

「北上夜曲」という曲名は知っていたものの、実際に聴いたのはこれが初めてでした。
歌詞を読むと、初恋、別れ、そして生きる強い意志が歌われており、どこか切なさを伴う曲です。
美空ひばりさんをはじめ、さまざまな歌手が歌い継いできた「北上夜曲」。
中でも、氷川きよしさんが公式YouTubeチャンネルで披露している歌唱は、現代においてこの曲の魅力を改めて感じさせてくれます↓
10代の学生が生んだ昭和の名曲
北上夜曲の成り立ちを調べてみたところ、流行に至るまでの経緯がとても興味深いものでした。
もともと「北上夜曲」は作者不詳の歌として、密かに人々の間で歌い継がれてきたといいます(参考:北上市ホームページ『広報きたかみ No.494』)。
その歩みは以下の通りです。
- 昭和16年(1941年):「北上夜曲」が誕生。作詞・作曲ともに当時は明かされず、“読み人知らず”の楽曲として広まる。
- その後:作詞者の菊地規さんが教師となり、自身の教え子たちに北上夜曲を伝え、地元で少しずつ知られるように。楽譜や音源のない中、人から人へ口伝えで歌が受け継がれる。
- 昭和30年代:歌声喫茶ブームとともに全国的に大ヒット。
- 昭和36年(1961年):ようやく菊地さんと作曲者の安藤睦夫さんが名乗りを上げ、曲の由来が公に。
さらに驚いたのは、作詞・作曲を手がけたお二人の年齢です。
当時、菊地さんは18歳、安藤さんは17歳の学生で、いずれも音楽を専門的に学んでいたわけではなかったそうです(現在はお二人とも故人)。
作曲者の安藤さんは旧制八戸中学校の生徒で、菊地さんとは安藤さんの叔父が水沢農学校の配属将校だったことをきっかけに出会ったとのこと。
あの若さで、あれほど切なく美しい旋律を紡いだことに、ただただ感嘆するばかりです。
北上夜曲という名曲とともにお二人の才能も、これからも語り継がれていくのだろうと感じました。
展勝地に刻まれた記憶と川の風景
北上夜曲の発祥地は現在の奥州市(水沢地区)ですが、北上市の展勝地に歌碑が設置された理由について、『広報きたかみ No.494』によれば、「曲に歌われた風景が展勝地の北上川河畔を連想させる」とのこと。
たしかに、この日見た北上川の風景は印象的でした。
初夏の晴天の下、川面がキラキラと光り輝き、新緑が心地よく揺れる景色に、時を忘れて見入ってしまいました。


奥州市にも同様の歌碑があるとのことなので、機会があればぜひそちらにも足を運び、北上夜曲が歌った風景を改めて感じてみたいと思います。
- 訪問場所:北上夜曲の碑(展勝地レストハウスを出てすぐ)
- 住所 :岩手県北上市立花14地割21−1(展勝地レストハウス)
- 訪問時期:2023年6月