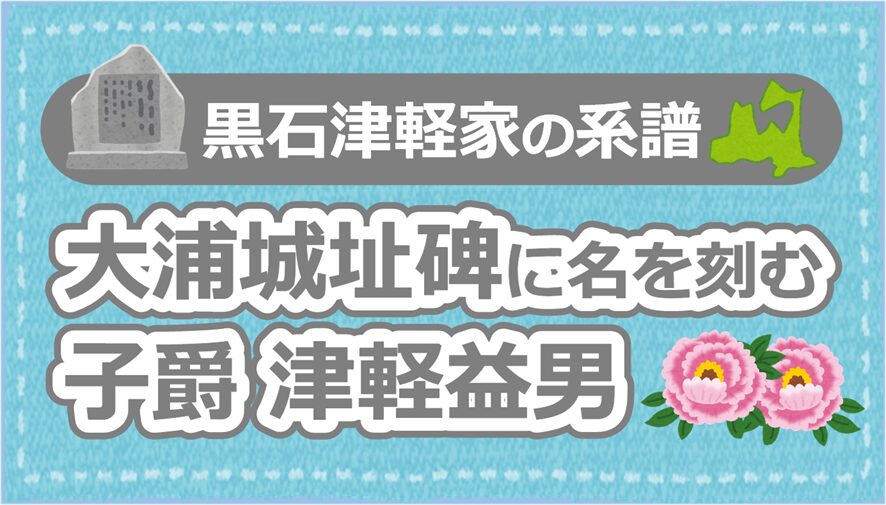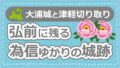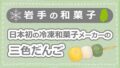青森県弘前市五代早稲田に建つ「大浦城址碑」。
前回の記事では、この碑が示す大浦城の歴史や「津軽切り取り」と呼ばれる出来事についてご紹介しました。
今回は視点を変え、この碑に刻まれた文字「大浦城址 子爵津軽益男書」に注目します。
碑の揮毫者である津軽益男は黒石藩を治めた津軽家の当主であり、津軽為信の流れを継ぐ黒石津軽家を相続した先人です。
黒石津軽家13代当主・津軽益男

碑に名を残した津軽益男は、黒石津軽家の第13代当主で爵位は子爵。
『津軽黒石藩史』によれば、益男は明治時代に因州鹿奴藩(現・鳥取市)の池田家に生まれ、のちに黒石津軽家12代・類橘の養子となり家督を継ぎました。
ちなみに、12代・類橘の母(11代・承叙の正室)も池田家の出身であり、両家は二代に渡って縁戚関係を重ねています。
黒石津軽家は、弘前藩の支藩として約400年にわたり続いてきた家柄。
祖となったのは、弘前藩2代藩主・津軽信枚の二男、信英です。
その後、黒石津軽家8代・親足の時代に黒石藩が成立し、親足は初代藩主となりました。
また、歴代当主のうち6代・寧親と9代・順徳の二名は本家を相続し、弘前藩の藩主も務めています。
特に寧親は、弘前市の高照神社に残る随神門や廟所門を建立した藩主として知られます。
一方で、江戸後期の「相馬大作事件」で命を狙われるなど、波乱の時代を生きた人物でもありました。

皇紀2600年と大浦城址碑

津軽益男に話を戻します。
大浦城址碑の建立は昭和15年(1940)12月23日。
碑の側面にはその日付が刻まれています。
この年は神武天皇即位から2600年を記念する「皇紀2600年」にあたり、日本全国で奉祝事業が行われました。
ちょうど12月23日は、当時の皇太子(現・上皇陛下)のお誕生日でもあり、特別に意義深い日付といえるでしょう。
『青森県議会史』によると、同年11月に東京で開催された皇紀2600年奉祝式典には、青森県から約250名が参加しており、その名簿に津軽益男も記載されています。
まさに歴史的な節目に立ち会った人物が、大浦城址碑に揮毫したことになります。
大浦城を拠点に津軽統一を進めた津軽為信。
その居城跡に建てられた碑に、津軽家の子孫である益男の文字が刻まれたことは、当時の人々にとって誇り深い出来事であったと想像されます。
黒石津軽家の歴代当主
黒石津軽家は現在も存続しており、第15代当主は黒石神社(黒石市市ノ町)の宮司を務めています。
御祭神は初代・津軽信英です。
歴代当主の一覧を整理すると以下の通りです(参考:『津軽英麿伝』、津軽新報)。
- 信英(のぶふさ)
- 信敏(のぶとし)
- 政兕(まさとら)
- 寿世(ひさよ)
- 著高(あきたか)
- 寧親(やすちか)※弘前藩主
- 典暁(つねとし)
- 親足(ちかたり)※黒石藩初代藩主
- 順徳(ゆきのり)※後に弘前藩主
- 承保(つぐやす)
- 承叙(つぐみち)
- 類橘(るいきつ)
- 益男(ますお)
- 承捷(つぐかつ)
- 承公(つぐひろ)
津軽為信の拠点跡に建つ大浦城址碑。
その文字に刻まれた子孫・津軽益男の存在は、津軽家の歴史が今も地域に息づいていることを静かに物語っていました。
- 訪問場所:大浦城址碑
- 住所 :青森県弘前市五代早稲田
- 訪問時期:2023年9月
🧭 参考:2023年 弘前で巡った歴史スポット
<参考資料>
・津軽新報「平成24年6月20日(水)付紙面から」(http://www.shinpou.jp/2012_hpnews/news_0000/0620.html)
・森林助 編『津軽黒石藩史』,歴史図書社,1976. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9536726 (参照 2023-10-23)
・青森県議会史編纂委員会 編『青森県議会史』昭和11-15年,青森県議会,1973. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/3022539 (参照 2023-10-23)
・羽賀与七郎 著『津軽英麿伝』,陸奥史談会,1965. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2986800 (参照 2023-10-23)
※国立国会図書館デジタルコレクションの閲覧には、利用者登録が必要な場合があります。