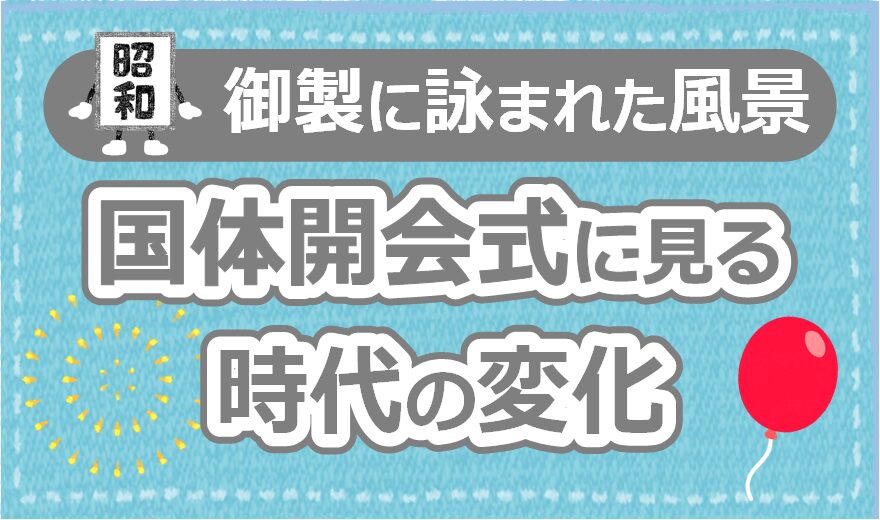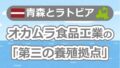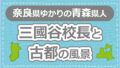令和8年(2026)、青森県で開催予定の国民スポーツ大会(国民体育大会の後身で、略称「国スポ」)。
先日ご紹介した記事で触れた通り、皇族方の御訪問に備え、青森県庁では「行幸啓室」という特別な部署が新設されました。
このニュースをきっかけに、青森県と国体の歴史にまつわる記事をシリーズで書いています。
前回のブログでは、昭和52年(1977)、青森県で開催された「あすなろ国体」の開会式で詠まれた昭和天皇の御製(天皇陛下が詠まれる和歌)について書きました。
「花火ひらき 風船あがり 青森の 秋の広場に 若きらつどふ」
この御製からは、花火と風船が開会式を彩り、秋の澄んだ空のもとに若者たちが集う光景が目に浮かびます。
そこで気になったのが、「昭和の国体の開会式では、他にどのような御製が詠まれたのか?」という点です。
今回は『昭和の御製集成』(出版:毎日新聞社、1987年)を基に、昭和天皇が国体開会式で詠まれた御製をご紹介したいと思います。
戦後復興・経済成長期(昭和20〜30年代)、高度経済成長期以降(昭和40〜50年代)に分けて見ていきましょう。
戦後復興・経済成長期(昭和20〜30年代)
終戦から間もない時期に始まった国民体育大会。
この時期の御製には、「若者」、「足なみ」、「集う」といった表現がたびたび登場し、戦後の困難な時代の中、国体に出場する若者たちの姿を見て喜ぶお気持ちが伝わってきます。
風さむき 都の宵に わかうどの スポーツの歌 ひびきわたれり
沖縄の 人もまじりて いさましく 広場をすすむ すがたうれしき
うれしくも 晴れわたりたる 円山の 広場にきそふ 若人のむれ
晴れわたる 秋の広場に 若人の つどふすがたの いさましきかな
足なみを そろへていまし 草薙の 広場につどふ わかうどのとも
ときどきの 雨ふるなかを 若人の 足なみそろへ 進むををしさ
山なみは 春ふかくして 広庭に あまたの鳩の そらたかくとぶ
若者たちの勇ましい姿にお喜びになる一方で、開会式は天候に恵まれなかったこともあったようで、「風さむき」、「雨ふるなかを」という表現が登場します。
そんな悪天候が戦後の困難な時代を暗示しているようで、その中に集まる若者たちの姿からは将来への希望のようなものが感じられます。
また、「足なみそろへ」という表現は、若者たちが一致団結して前へ進む姿を象徴しているよう。
秩序が失われた戦後から、日本が確実に再建していく姿が想像されます。
そして、昭和天皇の沖縄への思いが感じられるのが、昭和28年(1953)に四国四県で行われた開会式について詠んだ御製です。
当時占領下にあった沖縄県民の参加を昭和天皇が心から喜ばれている様子が、まっすぐに伝わってきます。
(それだけに、昭和天皇の沖縄行幸が叶わなかったのが残念でなりません)
高度経済成長期以降(昭和40〜50年代)
この頃から、御製には開会式で披露される郷土芸能や開催地の情景がしばしば詠み込まれるようになっていきます。
国体の開会式がスポーツの祭典であると同時に、地域文化を紹介する場としての意味合いを強めていったことがうかがえます。
一方、石油危機による社会情勢の変化を受け、昭和51年(1976)の佐賀国体では、大会の開催にあたり費用の大幅な見直しが行われました。
「ことそぎて(簡素にして)」に始まる御製からは、そうした状況下でも意義深い開催を成し遂げた佐賀県への労いの気持ちが感じられます。
秋ふけて この広庭に 子らはみな ふるさとぶりの をどり見せたり
長崎の あがたの山と 海の辺に わかうどきそふ 秋ふかみつつ
人びとは 秋のもなかに きそふなり 北上川の ながるるあがた
黒潮の うちよする紀伊(き)の 秋たけて けふあひきそふ 若人たちは
よべよりの 雨はいつしか ふりやみて 人びとはつどふ 千葉の広場に
南より 北より来つる 選手らの 常陸の秋に あひきそひけり
秋ふかき 三重の縣(あがた)に 人びとは さはやかにしも あひきそひけり
ことそぎて 秋の国体は ひらかれぬ 人々はつどふ 佐賀の広場に
花火ひらき 風船あがり 青森の 秋の広場に 若きらつどふ
また、昭和40年代以降、「きそふ(競う)」、「あひきそふ(競い合う)」という表現が頻出するようになることに注目したいところです。
戦後復興・経済成長期は若者たちが国体に集結する姿そのものを讃えていたのに対し、この時期は若者たちが競技に向き合う姿勢も尊ばれていたように思えます。
それにしても、これは青森出身者ゆえのひいき目もあると思うのですが、青森県開催の国体での御製は特に祝祭感にあふれているように思います。
私の上の世代の青森県の先人たちが、この国体成功のためにどれほど力を尽くしてきたのか。
この御製を読むたび、そう思うようになりました。
御製に見る昭和天皇にとっての国体
こうして国体の開会式を詠まれた御製を見ていると、昭和天皇にとっての国体は、健やかな国民の姿と開催地域の豊かさを知る大切な機会だったのではないかと感じます。
時代を経て日本が復興と発展を遂げ、それとともに昭和天皇のまなざしも変わられていったことが理解されます。
当時の日本の人々の姿、風景を知る意味においても、御製には貴重な文化資料としての価値もあると感じました。
今回は昭和の国体開会式に関わる御製のみをご紹介しましたが、今後も引き続き、時代ごとに詠まれてきた御製を調べていきたいと思います。
※本記事でご紹介した御製は、昭和62年(1987)に刊行された『昭和の御製集成』に掲載されたものをもとにしています。刊行当時はご在位中であったことから、全ての御製が網羅されているとは限らない点をあらかじめご承知おきください。
参考資料
- 『昭和の御製集成』,毎日新聞社,1987.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12686779 (参照 2025-07-15)
<ウェブサイト>
- 佐賀県ホームページ「佐賀県公文書館だより 第11号」(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00327947/3_27947_up_y37i7tri.pdf)(令和7年(2025年)3月発行)