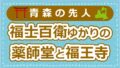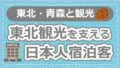先週末、2025年4月12日にNHK青森 NEWS WEBに掲載された地域ニュースの見出しを一覧にまとめました。
なかでも特に目を引いたのが、鶴田町の観光名所「鶴の舞橋」に関するニュースです。
この話題をきっかけに、鶴の舞橋が架かる津軽富士見湖の歴史についても少し調べてみました。
2025年4月12日の主な青森ニュース
2025年4月12日の主な青森ニュースは以下の通りです(参考:NHK青森 NEWS WEB)。
- 青森 米軍三沢基地で日本文化に触れる 「ジャパンデー」開催
- 青森 むつ ミャンマー大地震の被災者支援へ高校生が募金活動
- 青森 ヴァンラーレ八戸FC、大阪に敗北
- 青森 鶴田町の観光名所「鶴の舞橋」で観光ガイドが活動開始
ミャンマー支援、米軍基地での日米交流など、国際的な話題が並びました。
ミャンマーは親日国であり、留学生や技能実習生の活躍、オカムラ食品の進出など、青森とも深い結びつきがあります。
一刻も早い地震からの復興を祈ります。
鶴の舞橋の観光ガイドが始動
この中で今回取り上げるのが、 「鶴田町の観光名所『鶴の舞橋』で観光ガイドが活動開始」。
鶴の舞橋というと、JR東日本のCM「大人の休日倶楽部」で吉永小百合さんが紹介し、記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
私も訪れたことがありますが、橋から見える湖と岩木山の風景は、まさに絶景でした。
以下、鶴の舞橋に関するニュースを要約します。
青森県鶴田町の観光名所「鶴の舞橋」が春の観光シーズンを迎え、通行可能になりました。橋は全長約300メートルの木造で、現在老朽化に伴う改修工事が行われており、ヒバやスギといった県産材が使われています。地元の観光ガイドは、橋の見どころや岩木山を背景にした撮影スポットを確認し、案内の準備を整えました。
また、地元の保育園児たちも訪れ、ガイドとともに自然の風景を楽しみました。観光ガイドは予約制で、今年は11月中旬まで活動が予定されています。
予約制で観光ガイドのサービスが実施されているんですね。
観光ガイドに案内してもらうと、見えてくる風景に深みが加わりますよね。
私も旅行の際は可能な限り観光ガイドのサービスを利用するようにしています。
津軽富士見湖の350年の歴史
この鶴の舞橋が架かる巨大な溜池の通称は津軽富士見湖。
津軽富士の異名を持つ岩木山が美しく見えることに由来します。
津軽富士見湖の正式な名称は、「廻堰大溜池(まわりぜき おおためいけ)」です。
廻(回る、囲む)+堰(水をせき止めるもの)という漢字から、「水をせき止めて巡らせるもの」という意味になります。
この名称から推測されるのは、この溜池の水を制御するために、先人がインフラ整備を行ったのではないか、ということです。
現在の廻堰大溜池は水がしっかりコントロールされ、観光地「津軽富士見湖」の印象が強いですが、そこに至るまでの歴史を調べてみました。
新田開発と堤防の整備
調べてみると、この廻堰大溜池が用水地として整備されたのは、約350年前、弘前藩が津軽一帯を治めていた時代です。
これにより、西津軽の広須新田が開拓され、津軽の農業が発展していきました。
この廻堰大溜池は現在でも農業用水として活用され、「西津軽一円の農業にとっては欠くことのできない重要な役割」を果たしています(引用:農林水産省ホームページ「特色のあるため池の紹介」)。
西津軽とは、現在のつがる市を中心とする地域のことで、廻堰大溜池もかつて西津軽郡に属していました。
Googleマップの航空写真を見てわかるように、廻堰大溜池の北方につがる市の大穀倉地帯が広がっており、南西には水源地である岩木山がそびえています。
もともとは自然の貯水池
廻堰大溜池はかつては岩木山を水源とする白狐沢からの自然流水による貯水池として存在していました。
Googleマップ上で見ると以下の通りで、岩木山を水源地としていることがわかります。
今から遡ること約450年、安土桃山時代の津軽。
天正5年(1577)、後の弘前藩初代藩主となる津軽為信が西津軽の広須野の巡回を行ったことが記録からわかっています。
その当時、この一帯では戦国の落武者による開拓が行われていたものの、十分な成果を挙げられずにいました。
“中興の祖“による新田開発
それから約100年後、四代藩主・津軽信政は岩木川下流域の新田開発に乗り出しました。
津軽信政と言えば、弘前藩中興の祖と言われる名君で、以前ブログにも書きましたが、高照神社(弘前市)に祀られている藩主です。
例えば、以下のような功績が知られています。
- 岩木川の治水
- 津軽新田の開発
- 屏風山の植林
- 「津軽古文書」を編集
三つのインフラ整備と文化的事業の整備を行った津軽信政は、まさに中興の祖。
強いリーダーシップを持ち、また、優れた家臣にも恵まれた藩主だったのでしょう。
廻堰大堤奉行、樋口権右衛門
西津軽の新田開発を進めるために信政が命じたのが、廻堰大溜池の整備でした。
万治3年(1660)、信政は西津軽の貯水池に堤防を築き、農業用水池として整備すべく、樋口権右衛門を「廻堰大堤奉行」に任命します。
西津軽の開拓地である広須新田は湿地帯で、「流れが方々から集まり、人馬の往来も困難を極めたような状態」だったといい、水害、旱害の被害も懸念されていました(引用:『青森県人名大事典』)。
この状況を打開するため、広須新田の南方にある貯水池の大規模な工事が必要だったのです。
廻堰大溜池の難工事が完了したのは、寛文4年(1664)。
樋口権右衛門が廻堰大堤奉行を拝命してから4年の月日が経過していました。
ところで、この樋口権右衛門という家臣、ここまでの大工事を遂行した人物だから、その後も弘前藩のインフラ事業に携わっていてもおかしくないと思うのですが…
記録上では、彼の名前はこの事業にのみ見られます。
単純に私の調べが不足しているだけかもしれませんが、歴史書の記述が少ないのが意外なように感じます。
農業用水池から「富士見湖」へ
こうして信政が命じ、樋口権右衛門が完成させた廻堰大溜池。
津軽の自然は厳しく、特に豪雨や岩木山からの融雪が原因で堤防の決壊が相次ぎ、元禄・寛政・文政・明治・大正の各時代に大修理が行われました。
そして現代、昭和35年(1960)に現在の堤防が完成。
それは、津軽信政が樋口権右衛門を「廻堰大堤奉行」に任命してから、ちょうど300年目にあたる年でした。
総工事費は当時の金額で約4億円。現在の物価に換算すれば、数十億円に相当する大工事でした。
それだけ西津軽の穀倉地帯にとって不可欠な存在だったのでしょう。
そして、平成6年(1994)、日本一長い木造三連太鼓橋「鶴の舞橋」が完成。
湖水の管理の機能を持ちつつ、景観としても非常に優れた橋が架けられました。
資材に用いたのは総ひば材で、橋脚には樹齢150年の青森ひばを使用、伝統技術も採用されました。
歴史ある場所に歴史ある木材と技術を使って橋を架ける。
その発想には先人と廻堰大溜池への敬意が感じられ、とても素敵です。
西津軽の農業を支えてきた廻堰大溜池は、観光名所として地域経済を盛り上げていくことになります。
廻堰大溜池と鶴の舞橋の年表
これまで見てきた流れを年表にまとめると、下記のようになります↓
| 和暦 | 西暦 | 出来事 |
| 天正5 | 1577 | ・津軽為信が西津軽の広須野を巡回 (低湿地帯で開拓が難航していた) |
| 万治3 | 1660 | ・弘前藩四代藩主・津軽信政が樋口権右衛門を「廻堰大堤奉行」に任命 |
| 寛文4 | 1664 | ・廻堰大溜池の整備が完了 |
| (経過) | ・元禄・寛政・文政・明治・大正の各時代に大修理を実施 | |
| 昭和16 | 1941 | ・県営築堤事業が開始 |
| 昭和35 | 1960 | ・現在の堤防が完成し、西津軽地域の重要な農業用水供給源となる |
| 平成6 | 1994 | ・鶴の舞橋が完成 |
| 令和5 | 2023 | ・鶴の舞橋の大規模改修工事開始 |
| 令和8 | 2026 | ・鶴の舞橋の工事完了(予定) |
ただの“映える橋”じゃない
こうして見てみると、鶴の舞橋 はただの“映える橋”じゃないんですよね。
背景には、津軽の人々が何百年もかけて自然と向き合いながら築いてきた歴史があります。
また、先日のブログでは、津軽信政の祖父である二代藩主・信枚が江戸に津軽の米を輸送すべく青森港整備に着手したことについて書きました。
信政が切り拓いた田んぼで採れた米が、祖父の信枚が整備した港を通って江戸へと運ばれていった………そんな光景を思い描くと、世代を超えた歴史の積み重ねを感じます。
今度訪れるときは、ぜひ観光ガイドさんの案内付きで歩いてみようと思います。
参考資料
- 「青森県鶴田町 | 鶴の舞橋」(http://www.town.tsuruta.lg.jp/kankou/kankou-kankou/tsurumaihashi.html)
- 「道の駅つるた 「鶴の里あるじゃ」 – 鶴田町」(http://www.town.tsuruta.lg.jp/syoukai/syoukai-kouhou/document/201602_23.pdf)
<ウェブサイト>
- NHK青森放送局 青森 NEWS WEB
- JR東日本:東日本旅客鉄道株式会社「青森県『津軽の逆さ富士篇』」(https://www.jreast.co.jp/otona/tvcm/sakasafuji.html)
- 政府広報オンライン「鶴の舞橋(つるのまいはし)日本一の木造三連太鼓橋」(https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202309/202309_07_jp.html)
- 農林水産省ホームページ「特色のあるため池の紹介」(https://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/pdf/toku_syoku_2_aomori_mawari_zeki.pdf)
- 弘前市ホームページ「白狐沢堤」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/nogyo/files/byakkozawatameike.pdf)
- 日本一長い木造三連太鼓橋「鶴の舞橋」大改修おっかけサイト
<国立国会図書館デジタルコレクション>
- 西津軽郡 編『西津軽郡統計書』大正元年,西津軽郡,大正2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/973769 (参照 2025-04-16)
- 東奥日報社 編『青森県人名大事典』,東奥日報社,1969. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12188662 (参照 2025-04-16)
※タイトルのイラストは、Googleストリートビューの風景を参考にAIで生成した創作イラストです。元画像をそのまま使用したものではなく、商用利用を目的としたものではありません。