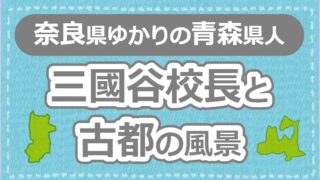 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 【奈良県ゆかりの青森県人】奈良県師範学校・三國谷三四郎校長が語る古都の風景
つい先日、Amazon Photosから「数年前のこの日に撮った写真です」という通知が届きました。表示されたのは、奈良公園で出会った鹿さんや東大寺など、以前奈良を訪れた際に撮影した風景の数々です。写真を眺めながら、郷土史好きの私はこんなこと...
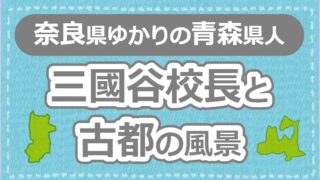 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 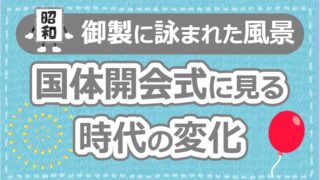 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 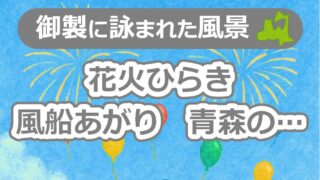 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 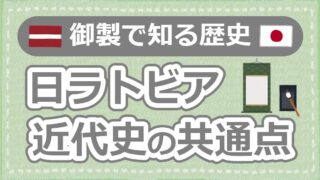 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 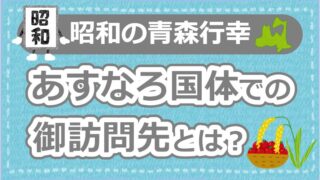 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 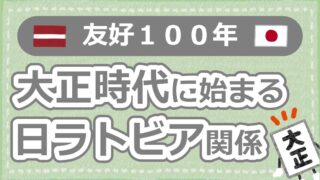 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 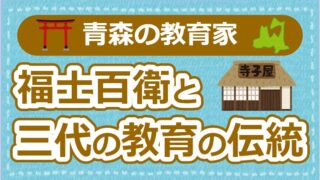 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 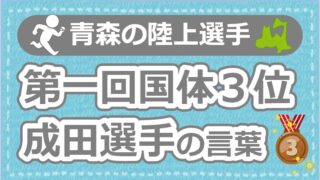 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 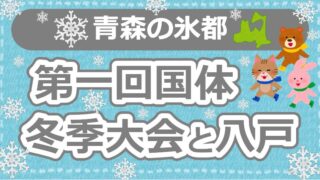 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ 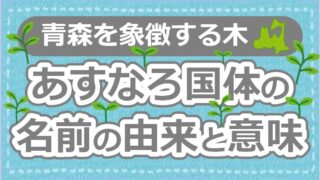 歴史を学ぶ
歴史を学ぶ