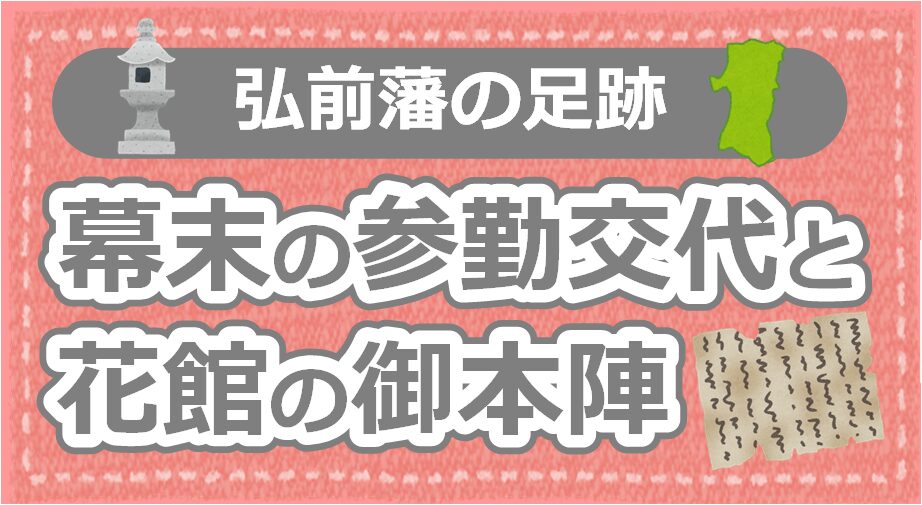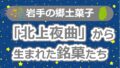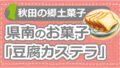秋田県大仙市の花館地区。
ここは、かつて羽州街道の宿場町としてにぎわった歴史を持ち、現在も当時の名残を感じられる場所です。
以前書いた記事(【弘前藩の足跡】秋田に残る本陣と駅場跡を歩く)では、弘前藩主が参勤交代の際に立ち寄った花館の駅場や、御本陣跡の庭園についてご紹介しました。
今回の記事はその続編として、御本陣を務めた斎藤家に残る幕末の文書「請書(うけしょ)」を中心に、弘前藩と花館のつながりをさらに深掘りしてみたいと思います。
弘前藩主を迎えた御本陣と花館の斎藤家
花館コミュニティセンター周辺には、かつて弘前藩主の御本陣となった斎藤家の屋敷がありました。
前回の訪問では、その庭園跡に灯籠や石畳が残っている様子をお伝えしましたが、今回改めてその歴史的背景を調べてみました。

斎藤家は、文人を多く輩出した風雅な家柄で、近代では第一回衆議院選挙で当選した斎藤勘七を輩出しています。
勘七もまた俳句を嗜んだとされ、文化的な伝統が脈々と続いていたことがうかがえます。
嘉永7年、斎藤家が出した請書とは?
参勤交代の際、御本陣には事前に家臣が派遣され、日程を告げるという作業が必要でした。
『写真に見る花館の歴史』(花館の会編)には、嘉永7年(1854)に斎藤家が弘前藩(書籍では津軽藩と記載)の家臣に提出した請書の内容が紹介されています。
請書には「差上申請書之事」という表題があり、短い漢文で「謹んでお引き受けします」といった趣旨の返答が記されています。
文末には屋号「斎藤勘左衛門」の署名と止め印があり、御本陣の責任と格式の重さが伝わってきます。
この年はペリー来航の翌年。藩主は第11代津軽順承で、日本全体が揺れ動く幕末期にあたります(次の12代承昭が最後の津軽藩主)。
そんな緊張感が漂う時代に、この文書は取り交わされていました。
斎藤家に派遣された弘前藩家臣・木村門弥
この請書の宛先となったのが、弘前藩家臣・木村門弥という人物です。
国立国会図書館デジタルコレクションに所蔵されている『岩木町誌』には、門弥と同名の人物が、明治10年(1877)に弘前市高岡の高照神社へ、長男・木村静三とともに弓と矢を奉納した記録が残されています。
この門弥が、嘉永7年の参勤交代で花館に派遣された人物と同一である可能性は高いと考えられます(もちろん、代を継いだ別人の可能性も否定はできません)。
木村門弥のお役目である御本陣への事前派遣は、参勤交代中の藩主の安全を確保するうえで、非常に重要な任務だったと思われます。
道中の警備状況なども確認していたのではないでしょうか。
激動の幕末にそうした任を担い、その後も藩主ゆかりの神社に奉仕していたとすれば、木村門弥は藩主との間に深い信頼関係を築いていた人物だったのではないか?そう推測されます。
ところで、以前書いた記事でご紹介した弘前藩出身の実業家・木村静幽(弘前市在府町生まれ)もまた「木村」姓でした。
木村静幽は弘前藩主の側近だったとされており、もしかすると門弥とは親戚関係にあったのかもしれません。
同じ時代に、異なる形で津軽藩を支えた二人の「木村」。木村家の歴史が少し気になってきました。
大仙市花館の御本陣跡からは、弘前藩の参勤交代を支えた花館の人々の営みが確かにあったことを感じさせます。
秋田の地にも残された弘前藩の歴史を、これからも追っていきたいと思います。
- 訪問場所:花館コミュニティセンター(大仙市花館公民館)
- 住所 :秋田県大仙市花館上町5−19
- 訪問時期:2023年5月
<参考資料>
・『岩木町誌』,岩木町,1972. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9569016 (参照 2023-07-26)
・『写真に見る花館の歴史』,花館の会,大曲市花館財産区,昭和59年.