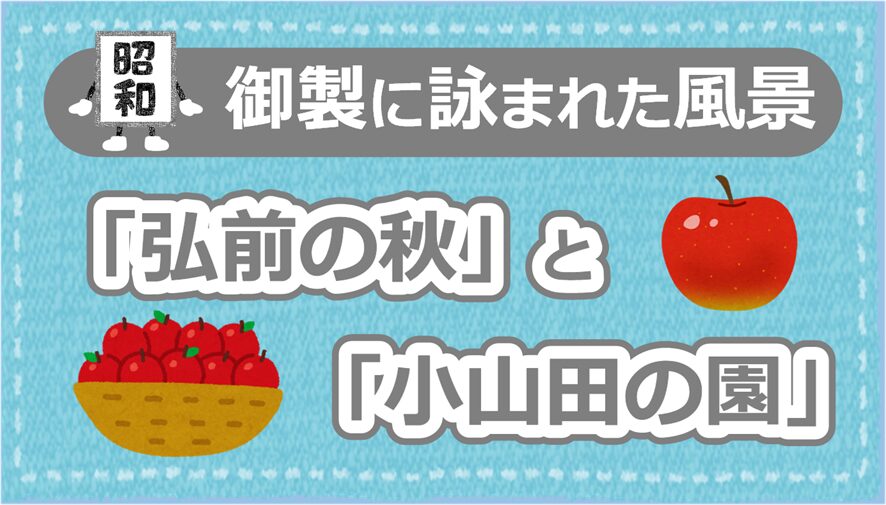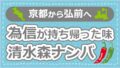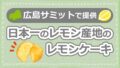令和8年(2026)、青森県での令和初となる国民スポーツ大会(旧・国民体育大会)の開催に伴い、皇族の来県に備えて青森県庁に「行幸啓室」が新設されました。
これに関連し、先日書いたブログでは、今から約半世紀前、昭和52年(1977)に青森県で初開催された「あすなろ国体」の開会式の際、昭和天皇が詠まれた御製(天皇陛下による和歌のこと)について取り上げました。
実はこの青森行幸の際、御製はさらに二首詠まれており、今回はそのうちの一首について考えを巡らせていきます。
このときの季節は秋。まさにりんごの収穫期を迎えた弘前の風景が御製に詠まれていますが、そこには「小山田の園」という言葉が登場します。
🧭関連記事:
弘前の秋を詠んだ御製
りんごの収穫期を迎えた青森県を訪れ、昭和天皇は以下の御製をお読みになりました。
弘前の 秋はゆたけし りんごの実 小山田の園を あかくいろどる
出典:『行幸啓誌』
りんごの名産地・弘前の秋の風景を詠んだこの御製。
ここに登場する「小山田」とは、弘前市石川小山田であると考えられます。
石川はりんごの名産地として知られている地区。
同地区にある大佛公園にはこの御製碑が建てられており、小山田のりんごの園が御製に詠まれたことは地域の誇りになっています。
しかし、当時の行幸記録には、昭和天皇が石川小山田を訪れたという記載はありません。
では、なぜ御製に小山田が登場したのでしょうか。
はっきりとした資料は見つかっていませんが、ここでは二つの仮説を考えてみます。
仮説① 御訪問先での御説明を受けて詠んだ?
『行幸啓誌』(出版者:青森県、出版年月日:1978.2)によれば、竹内俊吉知事は県勢概要御説明の中で、りんごを繰り返し取り上げていました。
「本県におきましては……現在は、米も、りんごも豊かな稔りの秋を迎えております。……『県の木』はヒバでありますが、『県の花』はりんごの花であります。……りんごは100年の歴史をもっておりますが、常に新品種の開発、栽培技術の向上に努めております。」
(『行幸啓誌』青森県,1978より)
この御説明からわかることは、以下の三点です。
- りんごが米と並ぶ基幹作物として強調
- りんごの花が県を象徴する花として紹介
- りんごの新品種開発や栽培技術向上を報告
随所でりんごが取り上げられ、しかも行幸の時期(10月)はちょうど収穫期の始まり。
昭和天皇は改めて「青森=りんごの名産地」という印象を強く持たれたのかもしれません。
その後の御日程でも、黒石市の青森県りんご試験場を御訪問されています。
試験場では作柄の説明を受け、赤く実った果実を昭和天皇ご自身で摘まれる場面もありました。
その次の御訪問先である弘前市役所でも市勢説明が行われたと思われますが、その資料は現時点では見つけられていません。
ただ、りんごの収穫について触れられたと考えるのが自然でしょう。
その際、小山田のりんご園の写真や映像が紹介された可能性もあります。
小山田のりんご園は傾斜地に広がっていることから、栽培技術の文脈で取り上げられることがあったのかもしれません。
仮説② 小山田の園を御覧になって詠んだ?
次に、昭和天皇が実際に小山田の園を御覧になった可能性を考えてみます。
小山田が位置する石川は、かつて明治天皇が立ち寄られた土地でもあります。
そのため、「祖父の足跡を意識して石川方面を経由されたのではないか?」という想像も成り立ちます。
しかし現実的に考えると、この可能性は低いようです。
小山田方面に行くとすれば、黒石市の青森県りんご試験場から弘前市役所に移動する際ですが、『行幸啓誌』に記された移動時間は約40分。
Googleマップで現在の小山田経由ルートを試算すると約46分となります。
もちろん、当時の道路状況と完全に一致するわけではありませんが、目安として考えると、御日程に記された40分を超えてしまいます。
加えて、警備上の理由からも、遠回りするのは難しかったでしょう。
したがって、「小山田をご覧になったうえで御製に詠んだ」という仮説は現実的には可能性は低いと思います。
「小山田の園」が少しだけ身近に
こうして見てみると、小山田の園が御製に登場した理由は、現存資料からは明確にわかりません。
けれども、青森県庁での県勢御説明、黒石市でのりんご摘みの体験、弘前市役所での御説明などが折り重なって生まれた一首だったのではないでしょうか。
確証はありませんが、想像を広げてみることで御製の中の「小山田の園」の風景が、少し身近に感じられる気がします。
もしかしたら、郷土史を調べていくうちに、この御製に関する新しい事実が見つかるかもしれません。
そのときはまた、ブログでご報告いたします。
参考資料
- 『行幸啓誌』,青森県,1978.2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12261230 (参照 2025-08-28)
- 『昭和の御製集成』,毎日新聞社,1987.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12686779 (参照 2025-08-28)
- 星野武男 編『明治天皇行幸史録』,潮書房,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1236359 (参照 2025-08-28)
※国立国会図書館デジタルコレクションの閲覧には、利用者登録が必要な場合があります。