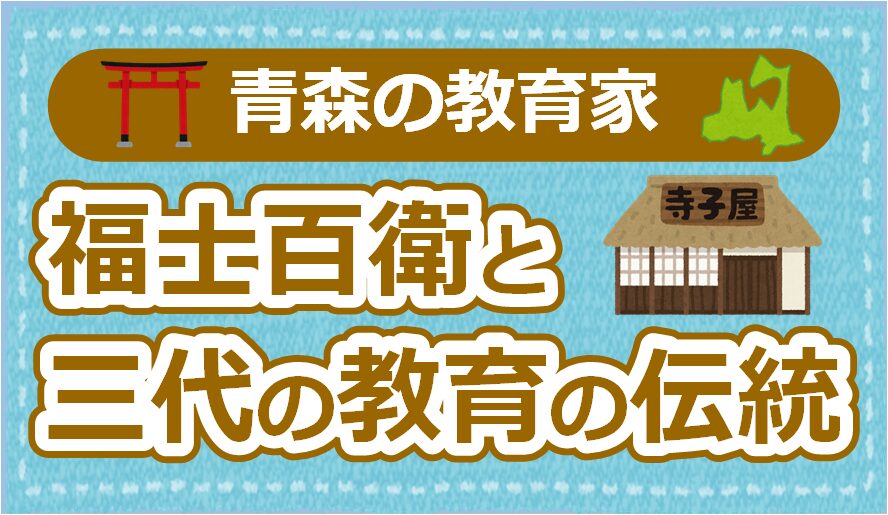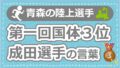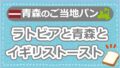亡き祖父の恩師である青森の教育家・福士百衛(ももえ)氏について調べています。
福士百衛氏は明治中期に生まれ、東京高等師範で学んだ後、秋田や青森で教鞭をとり、やがて青森の教育行政にも深く携わることになります。
前回のブログでは、福士百衛氏と父・福士武雄氏は教職を退いた後に神官を務めたという経歴が共通していることについて取り上げました。
今回は、福士百衛氏の生家、福士家の系譜について探っていきます。
前回までのおさらい
少し内容が複雑になってきたので、まずは前回までのおさらいをします。
福士百衛氏と父・武雄氏
- 福士百衛氏は明治中期に生まれた教育者で、退職後に神官として奉仕した
- 福士百衛氏の父、武雄氏も教育者であり、神官だった(父子共通の職歴)
- 父子がともに神官として奉仕していたのは、地元・薬師堂にある熊澤神社だった
- 福士百衛氏は隣村にある乳井神社にも神官として奉仕していた
福士百衛氏の地元・薬師堂と隣村の乳井
- 薬師堂は弘前市東部に位置し、地名は日照田にあった薬師堂に由来
- 薬師堂は隣村の乳井の福王寺による統治を受けていた
- 福王寺の後身は現在の乳井神社とされている
- その乳井神社に福士百衛氏は神官として奉仕していた
これらの事実から、薬師堂の福士家は地元の神社(熊澤神社や乳井神社)と深い関わりがあるのではないか?と推測しました。
福士家は熊澤神社の神官の家だった
これまでは官報や青森県の人名録を中心に調べていましたが、今回は福王寺が所在する乳井の郷土史を参照しました。
タイトルは『乳の井 : 津軽の或る部落史とその背景』で、乳井出身の伊藤勇蔵氏が著したものです。
この文献の熊澤神社に関わる箇所を読むと、福士武雄氏に繋がる福士家の系譜が記されていました。
その系譜によると、福士武雄氏は薬師堂の福士家の第35代にあたるとのこと。
文献の中では福士百衛氏への言及はありませんが、福士武雄氏の長男である福士百衛氏は第36代ということになります。
そして、この長い歴史を持つ薬師堂の福士家が代々神官を務めていたのが、薬師堂熊澤神社でした。
福士武雄・百衛父子が熊澤神社の神官を務めていたのは、自分たちの家が代々守ってきた神社だったからなんですね。
こうした歴史を知ったうえで改めて熊澤神社をストリートビューで見ると、より威厳があるように見えます…!
明治維新以前は地蔵院天台寺
熊澤神社は明治維新の神仏分離以前は、地蔵院天台寺という仏教の寺でした。
この時代の薬師堂の福士家は神官ではなく、寺の別当(寺務を統轄する僧官)。
そのため、江戸時代後期までの福士家の系譜に記載されている先祖は、全員「〇〇坊」「△△院」などの仏教的な名前でした。
世俗的な姓である福士を名乗るようになったのは、第34代福士安世(福士百衛氏の祖父)からです。
「安世」という名前には仏教的な意味が感じられることから、時代の移行期にちょうど居合わせていたことが伺えます。
福士百衛氏は明治23年(1890)生まれ。
もしかしたら、福士百衛氏が幼い頃にはまだ寺院だった頃の名残が熊澤神社に残っていたかもしれませんね。
祖父・安世氏も教育者だった!
前回のブログでは、福士武雄・百衛父子は二人とも教育者であり、神官だったと書きました。
このことに関連し、先述の文献に気になる記述を発見しました。以下、引用します。
私塾や寺子屋は文政(一八一八)から天保時代(一八四〇年代)にかけて小禄の藩士や僧侶、神官によって開校され、乳井村には隣村「薬師堂村」の熊沢神社(地蔵院天台寺、薬師寺とも言う)の別当「福士安世氏」が開校し子息「武雄氏」と続いた。福士家は乳井福王寺一門の名家で近年においても有名なる教育者を出している。
出典:「乳の井 : 津軽の或る部落史とその背景」
この記述からわかることは、福士百衛氏の祖父である福士安世氏も教育者だったということ。
神官として村の人々のために教育する場所(寺子屋)を作った、というところでしょうか。
「子息『武雄氏』と続いた」とあるので、武雄氏は父の安世氏より薬師堂における教育者としての役割を引き継いだと思われます。
明治13年(1880)に薬師堂小学校ができた後は、武雄氏は小学校教員の検定に合格し訓導として同校に勤め、最終的には校長を務めたことは前回のブログで紹介した通り。
また、「近年においても有名なる教育者」とは福士百衛氏のことを指しているのでしょう(この文献の出版当時、すでに福士百衛氏は故人)。
福士家は三代に渡って神官兼教育者だったということになります。
おそらく福士百衛氏は祖父と父が整備した薬師堂の教育の場で学んだと思われます。
福士百衛氏が教育者の道を選んだのは、祖父や父に望まれてのことだったのかもしれません。
その一方で、地域の教育振興に取り組んだ祖父、父の姿を見て、自然と教育者を志すようになった可能性もあります。
立場が人を育てるというか、家族と環境の影響を受けて立派な人間は育っていくと思うんですよね。
その後、福士百衛氏は東京高等師範学校で学ぶほどの人材になり、後年は私の祖父ら弘前中学の学生たちを教育する立場となりました。
「乳井福王寺一門の名家」?
この記述でもう一つ気になるのは「福士家は乳井福王寺一門の名家」というもの。
乳井福王寺といえば、現在の乳井神社(上記ストリートビュー)の前身と言われている寺。
また、乳井神社は福士百衛氏が神官として奉仕した神社でもあります。
この件に関しては、また後日詳しくまとめたいと思います。
福士安世・武雄・百衛の年表
教育者という経歴に注目した福士安世・武雄・百衛の簡単な年表を下記の通り作ってみました。
| 和暦 | 西暦 | 出来事 |
| 文政 ~天保 | 1818~ 40年代 | ・福士安世が薬師堂に寺子屋開校 |
| 安政2頃 | 1855頃 | ・福士安世の息子、武雄が誕生 ・後に父の後を継ぎ薬師堂の教育に携わる |
| 明治13年 | 1880 | ・薬師堂小学校が建設される |
| 明治23 | 1890 | ・福士武雄の長男、百衛が誕生 |
| 明治26 | 1893 | ・福士武雄が尋常小学校教員の検定に合格 (薬師堂小学校の訓導を経て、後に校長に就任) |
| 大正3 | 1914 | ・福士百衛が東京高等師範学校 国漢科卒業 ・祖父、父と同じ教育者の道に進む |
祖父、父が教育者として地域に貢献してきたからこそ、福士百衛氏の教育者としての歩みがあったんだなぁとしみじみ思います。
本記事のまとめ
- 福士百衛氏の家系は、薬師堂の熊澤神社(明治維新前は地蔵院天台寺)の神官を務めてきた
- 福士百衛氏の祖父・福士安世氏は薬師堂に寺子屋を作り、教育の場を整備した
- 福士百衛氏の父・福士武雄氏は薬師堂小学校の訓導を経て、後に校長を務めた
- 福士安世・武雄・百衛と薬師堂の福士家は三代に渡って神官と教育者を務めた
- 薬師堂の福士家は「乳井福王寺一門の名家」と呼ばれていた
私の祖父は福士百衛氏のことを尊敬していました。
私の祖父に影響を与えた福士百衛氏の言動やふるまいの背景には、薬師堂の教育者としての家系が関係していたのだと思います。
福士百衛氏の教えは私の祖父に確実に影響を与え、自分の子どもの教育にも活かしたと思われます。
そのつながりを感じると、薬師堂という地域に深いご縁を感じてきました。
いつか必ず薬師堂を訪れ、熊澤神社を参拝したいと思います。
参考資料
- 伊藤勇蔵 著『乳の井 : 津軽の或る部落史とその背景』,伊藤勇蔵,1981.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9570516 (参照 2025-05-19)
- 『学校幼稚園書籍館博物館一覧表』明治14年,文部省,[明15]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/812644 (参照 2025-05-19)
- 大蔵省印刷局 [編]『官報』1906年01月22日,日本マイクロ写真 ,明治39年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2950105 (参照 2025-05-19)