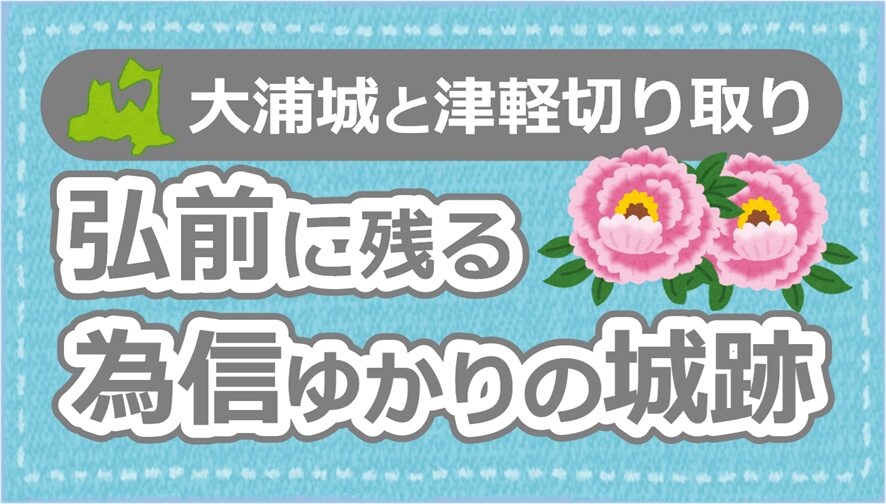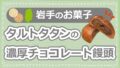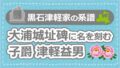青森県弘前市五代早稲田にある「大浦城址碑」を訪ねました。
かつてここは、弘前藩初代藩主・津軽為信が津軽地方を統一する過程で拠点とした城の跡地です。
「津軽切り取り」と呼ばれる出来事の舞台となり、その後の津軽と南部の対立の出発点にもなった場所。
現在は静かに佇む石碑を通じて、戦国から江戸へ続く歴史の一端を感じ取ることができます。
大浦城址碑のある場所
大浦城址碑は、弘前市五代早稲田にあります。
周辺には庁舎や学校、住宅が集まり、旧岩木町の中心地としての役割を果たしてきました。
長い年月を経た石碑には「大浦城址」と力強い文字が刻まれており、近くには弘前市立津軽中学校の校舎が見えます。
今は静かな雰囲気ですが、かつては人々の往来が盛んな場所だったことがうかがえます。

「津軽切り取り」とは?

大浦城は、大浦為信(のちの津軽為信)が津軽統一を進めた拠点でした。
近くにあった案内板の説明によると、経緯は次のとおりです。
- 文亀2年(1502):種里城(鰺ヶ沢町)城主、南部光信が築城
- 永禄10年(1567):大浦城主、為則の婿養子として為信が入城
- 元亀2年(1571):為信が石川城(南部氏の津軽支配の拠点)を攻略 → 津軽地方の領有を進める
- 天正18年(1590):豊臣秀吉から津軽地方の支配を事実上承認される
- 文禄3年(1594):為信が堀越城(弘前市堀越)に居城を移し、支城に
- 元和元年(1615):「一国一城の令」により廃城
大浦城の歴史は92年。
そのうち南部氏が約70年を治め、残りの20年で為信が南部氏を駆逐しました。
これが「津軽切り取り」と呼ばれる津軽統一の動きです。
さらに、この時期の為信にはもう一つ重要な転機がありました。
為信は京都の近衛前久に接近し、猶子となることでその庇護を受けます。
このとき「杏葉牡丹」の使用を許され、大浦から津軽へと改姓しました。
戦国の世らしく、主君を裏切ったとの評価もありますが、当時は実力がものを言う時代でした。
大浦城もまた、その激動の舞台となっていたことが理解されます。
津軽と南部の長い対立
為信による弘前藩の成立後も、南部氏との対立は続きました。
江戸時代には「相馬大作事件」と呼ばれる襲撃未遂(南部藩士が津軽藩主の襲撃を企てた事件)が発生。
幕末の戊辰戦争では、両藩が敵味方に分かれて戦います。
現代では「津軽と南部は仲が悪い」と冗談交じりに語られる程度で、テレビ番組などで弘前と八戸の比較が話題になることも。
争いが絶えなかった時代と比べれば、ずいぶん穏やかな関係に変わりました。
津軽と南部の争いの発端となった大浦城も、いまは石碑だけが残るのみ。
長い歴史を経て血なまぐさい時代が過去のものとなったことを実感します。
そして碑の近くには、「こごさ雪なげればまいねよ!」と書かれた看板が(意味は「ここに雪を捨ててはいけないよ」)。
かつて歴史の変動に揺れた地も、今は地域の人々の暮らしの場となっていました。

- 訪問場所:大浦城址碑
- 住所 :青森県弘前市五代早稲田
- 訪問時期:2023年9月
🧭 参考:2023年 弘前で巡った歴史スポット
<参考資料>
- 弘前公園総合情報「弘前公園の歴史」(https://www.hirosakipark.jp/history.html)