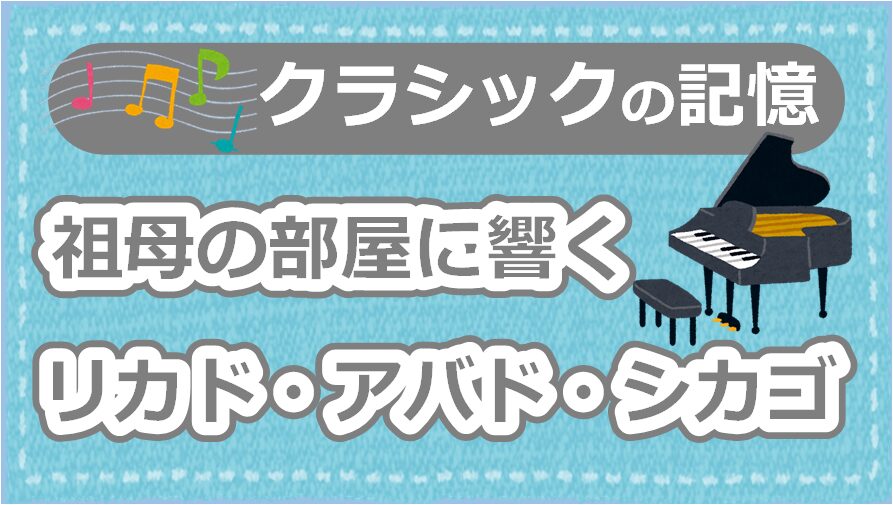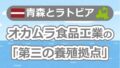子どもの頃、祖母の家で繰り返し聴いていたクラシックの名曲がありました。
それは、セルゲイ・ラフマニノフの《ピアノ協奏曲第2番》。
祖母の部屋にはソニー製の立派なオーディオがあり、そこから大音量でクラシックを流していたことをよく覚えています。
…とはいえ、夢中で聴いていると「ちょっと!音量大きいんだけど!」、「休むからどいて!」と祖母に注意されたことが何度あったことか。
ピアニストや指揮者の名前も知らず、演奏するオーケストラもわからないまま、ただラフマニノフという作曲家が作った曲に浸っていたあの頃。
思い返してみれば、それが私にとってのクラシックとの出会いだったのだと思います。
再びラフマニノフを聴き始める
やがて祖母の家に行くことはなくなり、クラシックも聴かなくなるように。
そんな私があらためてラフマニノフの《ピアノ協奏曲第2番》を耳にしたのは、ウラディーミル・アシュケナージの演奏でした。
この曲を聴くきっかけになったのは、ラフマニノフを主人公にした映画「ラフマニノフ ある愛の調べ」(2007年、パーヴェル・ルンギン監督)を観たこと。
劇中の冒頭で使われていたのが、アシュケナージが弾くピアノ協奏曲第2番だったのです(キリル・コンドラシン指揮、モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、1963年録音)。
それからというもの、その演奏ばかりを繰り返し聴くようになり、いつしか私の中でのラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の標準がアシュケナージ盤に置き換わっていきました。
ちなみに、この演奏はyoutubeでも聴くことができます↓(出典:ウラディーミル・アシュケナージ – トピック / YouTube)
昔聴いていたラフマニノフの演奏は?
いつものようにアシュケナージによるラフマニノフを聴いていた先日、ふと思ったのです。
「子どもの頃に聴いていた、あのラフマニノフは一体誰の演奏だったんだろう?」と。
思い出せたのは、CDジャケットにCBS-SONYと書かれていたことぐらい。
それだけを頼りに、ChatGPT先生に聞いてみることにしました。
さすがに「CBS-SONYから出ていたラフマニノフのピアノ協奏曲第2番」だけじゃヒント足りないだろうなーと思いながら質問したところ………
ChatGPT先生:セシル・リカド(ピアノ)、クラウディオ・アバド(指揮)、シカゴ交響楽団です。
この三者の名前が一瞬で返ってきたのです!そうそう、「リカド/アバド」ってジャケットに書いていた!
シカゴ交響楽団のことはさすがに覚えていなかったんですが、リカド・アバド・シカゴって語感がいいですね。
すぐにYouTubeで探してみると、ありましたありました。
初めて見るリカドとアバドの写真
以下がその音源を聴くことができるyoutube動画です↓(出典:セシル・リカド – トピック / YouTube)
動画のサムネイルになっているのは、ピアノの前で穏やかな表情を見せるピアニストのセシル・リカドと指揮者のクラウディオ・アバドが写るCDジャケット。
祖母の家にあったCDはクラシック全集の一枚で、ジャケットは西洋の名画が使われていたので、どんな人が演奏していたのかわからなかったんですよね。
ジャケットを見て思ったのは、「こんな素敵なコンビによる演奏だったのか」という感想でした。
音楽が記憶を呼び起こす鍵に
実際に聴いてみると、なんとも懐かしさがこみあげてくる旋律。祖母の部屋の記憶が鮮明に思い出されました。
自然光が入ってくる窓辺、部屋にかけられた祖母の服、ソニーのオーディオの存在感、そしてタンスにゴンの香り(祖母は贅沢使いしていたのか、けっこう香っていたんですよね)。
本棚に並べていた本のタイトルまで記憶に蘇ってきました。
祖母はすでに故人となり、ありし日の祖母の部屋を訪れたのはもう10年以上も前のこと。
記憶も薄れてきたように感じていましたが、人の脳というのは不思議とそうした光景をしっかりと覚えているものなんですね。
リカドのピアノ、アバドの指揮を語るほどの表現力は私にはありませんが、少なくともこの二人によるラフマニノフは私の記憶を呼び覚ます鍵のような存在であったのは確かです。
以前書いたブログで触れましたが、ブラームスの旋律が弘前の名曲喫茶の記憶を蘇らせてくれたこともありました。
そして、今回のリカド・アバド・シカゴ交響楽団のラフマニノフは、祖母の部屋の風景を思い出させてくれました。
…でも、一番鮮明によみがえるのは、「休むからどいて~」という祖母のくたびれた声だったりします。
ラフマニノフの名曲を背景に記憶の奥から現れるのは、そんな何気ない日常のワンシーンでした。
あのときの音色が忘れられない…そんな思い出のクラシック曲がある方は、試しにChatGPT先生に尋ねてみることをおすすめします。
意外なほどすぐに、その音の記憶へたどり着けるかもしれませんよ^^