先日、亡くなった大叔母のお墓参りに行ってきました。
大叔母が亡くなってから初めてのお参りで、ご親族の方から生前の様子やお墓にまつわるお話をうかがう機会にも恵まれました。
その中でも印象に残ったのが、「墓誌を残す」という選択。
自分や家族のお墓のあり方を考えるうえでも、重要な視点になりました。
合葬墓と墓じまい──大叔母のお墓から学んだこと
大叔母が眠っているのは、複数の方が一緒に供養される合葬墓です。
甥御さんが埋葬の手続きとあわせて、もとのお墓の墓じまいもしてくださったそうです。
最近では、少子化や家族構成の変化を背景に、合葬墓や共同墓地を選ぶ方が増えてきていると報じられています。
今回の訪問は、そうした流れが決して他人事ではないと実感する機会にもなりました。
墓誌を刻む意味──「いつか誰かが探しにきたときに」
甥御さんのお話で特に印象的だったのは、墓誌を刻印したという点です。
墓誌とは、お墓のそばに設置される石碑のことで、故人の戒名や没年月日、行年などが記されています。
実際、合葬墓のそばには石碑があり、大叔母のご家族のお名前も刻まれていました。
甥御さんによれば、「墓誌を刻まなくても埋葬はできたが、“いつか誰かが探しに来たときに見つけられるように”と思って刻印した」とのこと。
この言葉に、思わずハッとさせられました。
墓誌は“探す人”にとっての大きな手がかり
私自身、現在先祖調査を進めているところで、墓誌に刻まれた情報に助けられたことは何度もあります。
墓誌からわかる情報は以下の通り。
- 誰がそこに眠っているのかがわかる
- 戒名からその人の人柄を想像できる
- 命日や行年から、当時の時代背景が見えてくる
こうした情報は、戸籍や文書だけでは得られない、「個人の記憶」に通じる貴重な記録だと感じています。
墓じまいと墓誌のあり方──これからの選択肢
私たちの家族でも、これまで墓じまいについて話し合ったことがありました。
けれど、「墓誌を残すかどうか」という視点はこれまで意識していませんでした。
「お墓を継ぐ人がいない」という悩みは、今の時代では決して珍しくありません。
だからこそ、「どのように記録を残すか」という視点が、これからの供養や先祖とのつながりを考えるうえで、いっそう重要になっていくように思います。
私の親戚には小さな子どもたちが何人かいます。
その親御さんの中には「家系図ができたら教えてね」と言ってくれる方もいて、将来、子どもたちがご先祖のお墓を訪れたいと思う日が来るかもしれません。
たとえ墓じまいを選ぶとしても、墓誌のある合葬墓という形で何かを残せれば、未来の誰かがその記録にたどり着ける可能性があります。
今は娯楽が豊富な時代で、子どもたちが先祖調査に関心を持つ機会は少ないかもしれません。
実際、コロナ禍の影響もあり、私の親族もお墓参りをする機会が減ってしまいました。
それでも、「いつか誰かが探しに来たときのために」という視点は、これからの時代のお墓のあり方や記録の残し方を考えるうえで、大切にしていきたいと思いました。
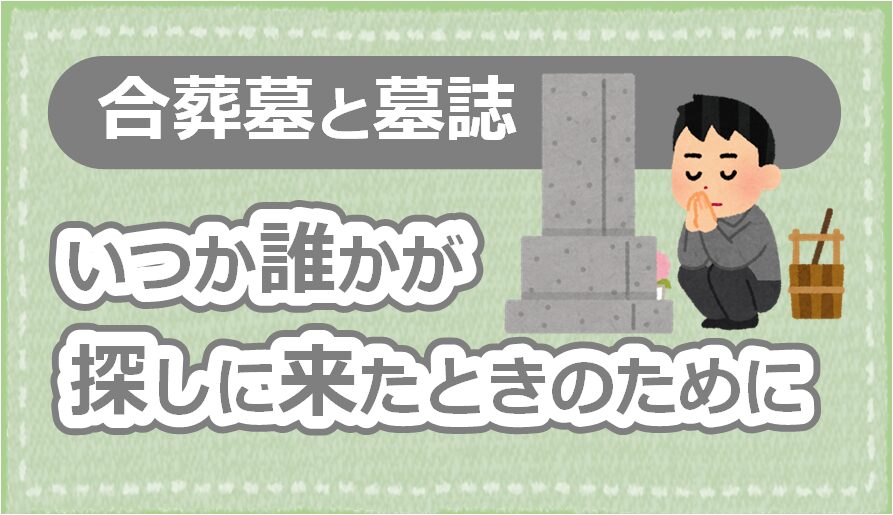
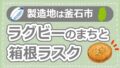
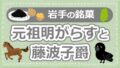
コメント