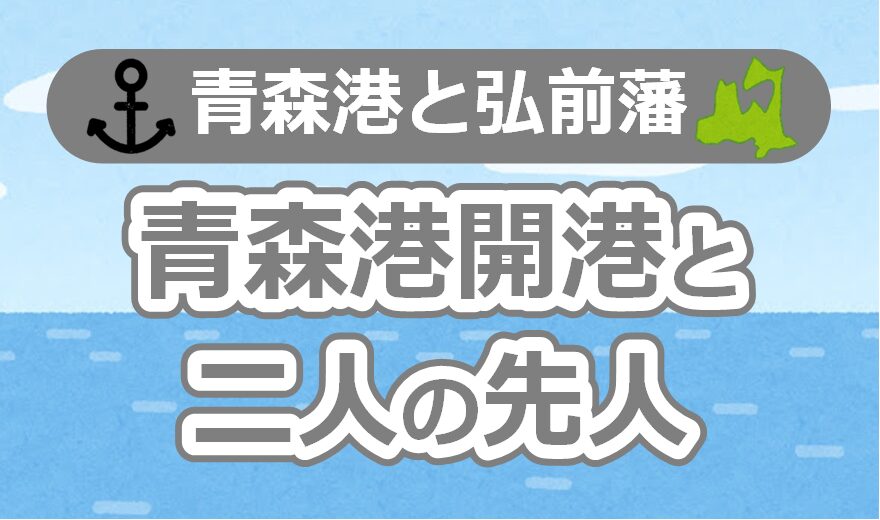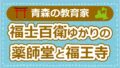2025年4月11日にNHK青森 NEWS WEBに掲載された地域ニュースの見出しを一覧にまとめました。
その中で今回気になったのは、青森港開港400年を祝うイベントを伝えるニュース。
青森港にそんなに長い歴史があるとは思わず、少し気になって調べてみました。
2025年4月11日の主な青森ニュース
2025年4月11日の主な青森ニュースは以下の通りです(参考:NHK青森 NEWS WEB)。
- 平内町 ホタテの選別作業進むも 漁業者は水揚げ量減を懸念
- 青森 「百日ぜき」感染 104人で過去最多 対策徹底
- 青森県 クマの被害防止へ訓練実施や管理計画策定の方針を確認
- 青森 八戸 水産加工会社「八光水産」が事業停止 自己破産へ
- 十和田 墺の芸術家エルヴィン・ヴルム氏が国内初の個展開催へ
- 山菜採りのシーズン 青森県が遭難防止へ対策会議
- 原子力機構 補償契約の手続きに不備 文部科学省から厳重注意
- 弘前の祭りにあわせ ことしも大館能代空港とのタクシー直行便
- 青森港開港400年 キックオフイベントに市民の参加呼びかけ
- 鰺ヶ沢 淡水魚「イトウ」の採卵 ブランド化目指して養殖
今年もクマ出没シーズンがやってきました。
各県クマの対応に頭を悩ませていますが、今年はどうか被害が起きないことを祈ります。
青森港に400年の歴史あり!?
歴史好きとして気になるのは、「青森港開港400年 キックオフイベントに市民の参加呼びかけ」。
青森県の歴史というと八戸や弘前に注目が集まりがちで、青森市は少し地味な存在かと思っていましたが、その港に400年の歴史があることは初知りです。
さて、このニュースの要約は以下の通りです。
青森港の開港400年を記念し、青森市は2025年に多彩なイベントを開催します。
4月27日には市民400人が参加し、800本のテープを青森ベイブリッジから投げ下ろす「出航テーププロジェクト」で幕開け。
また、7月には大型自衛艦や帆船「日本丸」の一般公開、9月以降には全国の水産物を使ったグルメイベントや港の歴史を題材にした演劇も予定されています。
西市長は「青森市の発展の歴史は、まさに港とともにある。歴史を振り返り、未来をみんなで考える年にしたい。イベントには1人でも多くの人に参加してほしい」と呼びかけました。
記事中に出てくる青森ベイブリッジはこちら↓奥には青森市のランドマーク、青森県観光物産館アスパムが見えます。
青森県で「400年の記念」と言えば、記憶に新しいのは2011年の弘前城築城400周年でしょう。
その築城から14年後の1625年、弘前藩の統治体制が固まりつつある中で、青森港の開港が進められていました。
物流の重要拠点・青森港
青森港は津軽半島と下北半島の間にある陸奥湾の奥に位置します↓
地図からもわかるように、青森港は本州と北海道を結ぶ物流の重要拠点であり、明治39年(1906)には特別輸出港(外国と貿易ができる港)に指定されました。
明治42年(1909)には、ロシア航路が政府の指定を受けて開設されています。
青森港については以前書いた平川市の盛美園のブログでも少し触れているのですが、盛美園が建設された当時(明治35~44年)の青森県は奥羽本線の開通やインフラ整備など近代化の波に乗っていた時期だったんですよね。
青森港が特別輸出港に指定されたのは1906年。この時点ですでに開港から約280年が経過しています。
それでは、青森港はどのような経緯があって開港に至ったのでしょうか?
弘前藩による青森港開港の歴史
弘前藩二代藩主・信枚による開港
今から400年前、青森港開港を推し進めたのは、弘前藩二代藩主、津軽信枚です。
そのきっかけは、寛永2年(1625)、弘前藩が津軽から江戸への廻船運航を幕府より許可されたこと。
これにより、弘前藩は津軽の米を江戸に輸送することが可能となります。
そこで、信枚が港として選んだのは陸奥湾に面した外浜(そとのはま)、現在の青森港のある地域でした。
幕府から廻船運航を許可され、開港に向けて着手した年を基準に開港400周年としているわけですね。
信枚の開港の指示により青森という町の歴史も始まっていくので、信枚がいなければ今の青森市はなかったかもしれませんね。
二代藩主・津軽信枚の功績
信枚は弘前城を完成させ、城下町を発展させた藩主として有名です。
弘前城と城下町だけでなく、青森港の開港にも深く関わっていたんですね。
以前、弘前藩の支藩である黒石藩に触れたブログを書いたことがあるんですが、黒石藩の祖はこの信枚の二男。
直接的に関わったわけではないにせよ、信枚の子孫によって黒石もまた発展の道をたどりました。
弘前、青森、そして後に支藩として成立した黒石。
それぞれの町の基礎となる要素に信枚の影響があったことを思うと、「難しい二代目」の役割を見事に果たした人物だったと改めて感じます。
家臣・森山弥七郎が青森へ
弘前藩が廻船運航の許可を得た翌年の寛永3年(1626)、信枚は家臣の森山弥七郎に開港とまちづくりを命じました。
この命を受け、弥七郎は青森へ赴き、開港の準備を開始。
青森港の整備は藩主導で行われ、下記のような施策が実施されました。
- 積極的な人寄
- 10年間の年貢等の免除
- 外浜一帯の商船を集中させる
つまり、今風に言うと、人口誘導政策と税制優遇措置と拠点集約といったところでしょうか?
さらに言うと、これらの政策は「積極財政」とも言えると思います。
当時の弘前藩は、弘前城の築城(1611年)から間もなく、城下町の整備や体制構築にも力を注いでいた時期と考えられます。
財政的には決して余裕があったとは言いがたく、そうした中での青森港への積極的な施策は、将来を見越した投資だったとも言えます。
こうした施策を担った弥七郎は、現代で例えるなら国土交通省と総務省を兼務するような役割だったのかもしれません。
相当の予算と人員を預かっていたと考えられますし、その責任は大きかったはずです。
それを成し遂げた彼は、非常に優秀だったのでしょう。
弥七郎はその功績から「青森開港の恩人」と称えられています。
青森港開港400年の年表
これまで見てきた流れを年表にまとめると、下記のようになります↓
| 和暦 | 西暦 | 出来事 |
| 慶長16年 | 1611 | ・弘前藩の居城、弘前城が完成 |
| 寛永2年 | 1625 | ・幕府から弘前藩に津軽・江戸間の廻船運航が許可される ・二代藩主・津軽信枚が外浜を港として選定 |
| 寛永3年 | 1626 | ・家臣・森山弥七郎により青森港の整備が開始 |
| 明治39年 | 1906 | ・青森港が特別輸出港に指定され、外国との貿易が可能に |
| 明治42年 | 1909 | ・ロシア航路が政府の指定を受けて開設 |
| 令和7年 | 2025 | ・青森港開港400周年 |
青森港の歴史に先人の先見と努力あり
つい先日、青森港にクルーズ船が寄港したというニュースを目にしましたが、弘前城を見に行くという観光客もいました。
津軽信枚も、青森港がここまで発展し、青森港から外国人観光客が弘前城に遊びに来るなんて光景、予想していなかったかもしれません。
信枚が開港に着手したこと自体は、幕府から廻船運航の許可が出た以上、ある意味当然の流れかもしれません。
しかし、信枚の着目した青森港がのちに大きく発展していくことを思えば、その判断にはやはり先見性があったと感じます。
青森港の歴史の裏には、津軽信枚や森山弥七郎といった人々の先見の明と努力があったのだと、改めて感じさせられました。
今年の400年イベント、青森の始まりに思いを馳せながら注目しようと思います。
参考資料
<ウェブサイト>
- NHK青森放送局 青森 NEWS WEB
- 青森市ホームページ 「青森市ホームページ・あおもり今・昔」(https://www.city.aomori.aomori.jp/area/aomoriayumi/im071.html)
- 青森市ホームページ 「有形文化財 森山弥七郎供養碑」(https://www.city.aomori.aomori.jp/bunka_sports_kankou/bunka_geijutsu/1005024/1005036/1005037/1005040/1005054.html)
- 財務省ウェブサイト 「ファイナンス 2021年10月号 No.671 48/94」(https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/denshi/202110/html5.html#page=49)
- 弘前市ホームページ 「津軽氏城跡」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/kuni/kuni29.html)